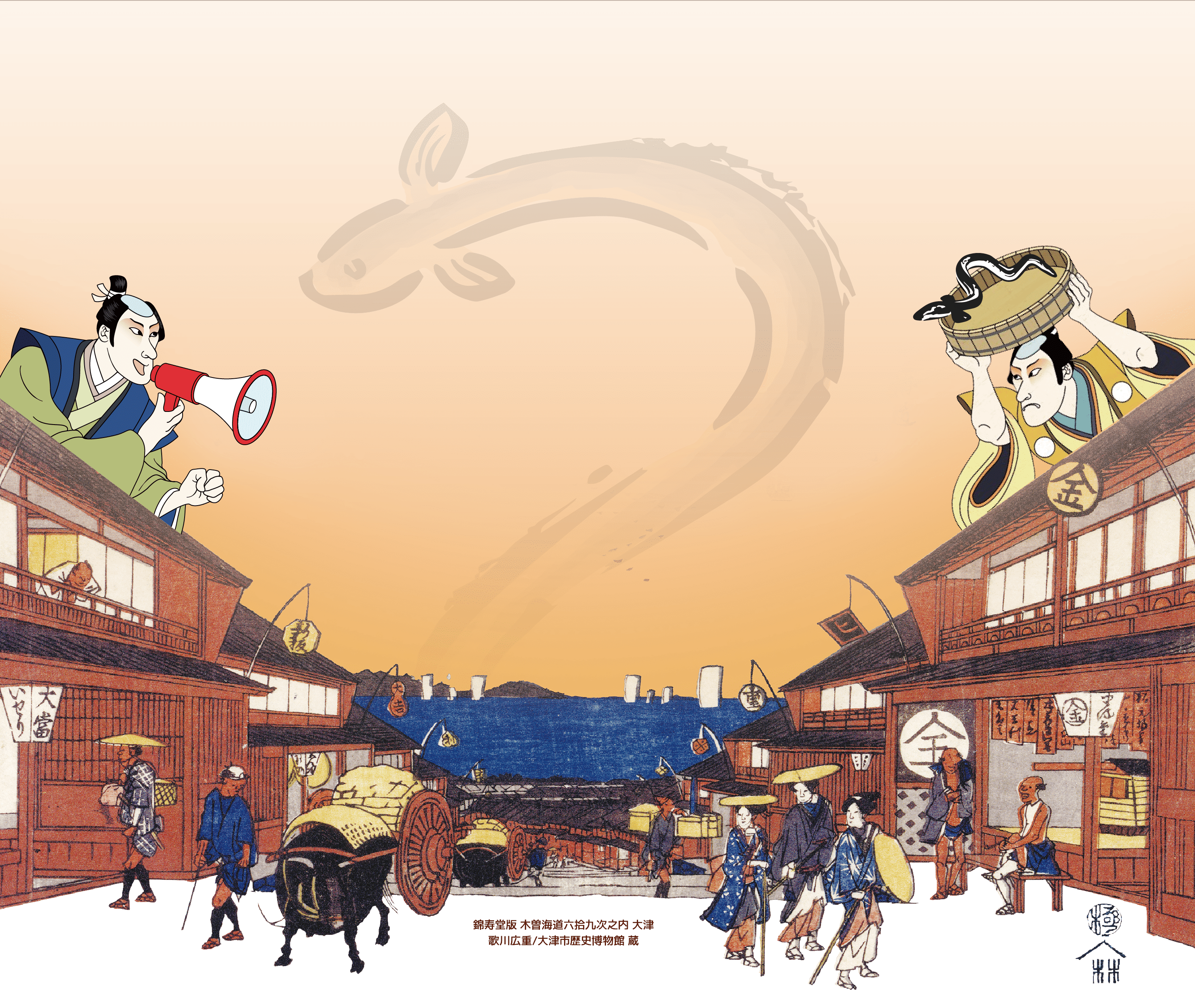
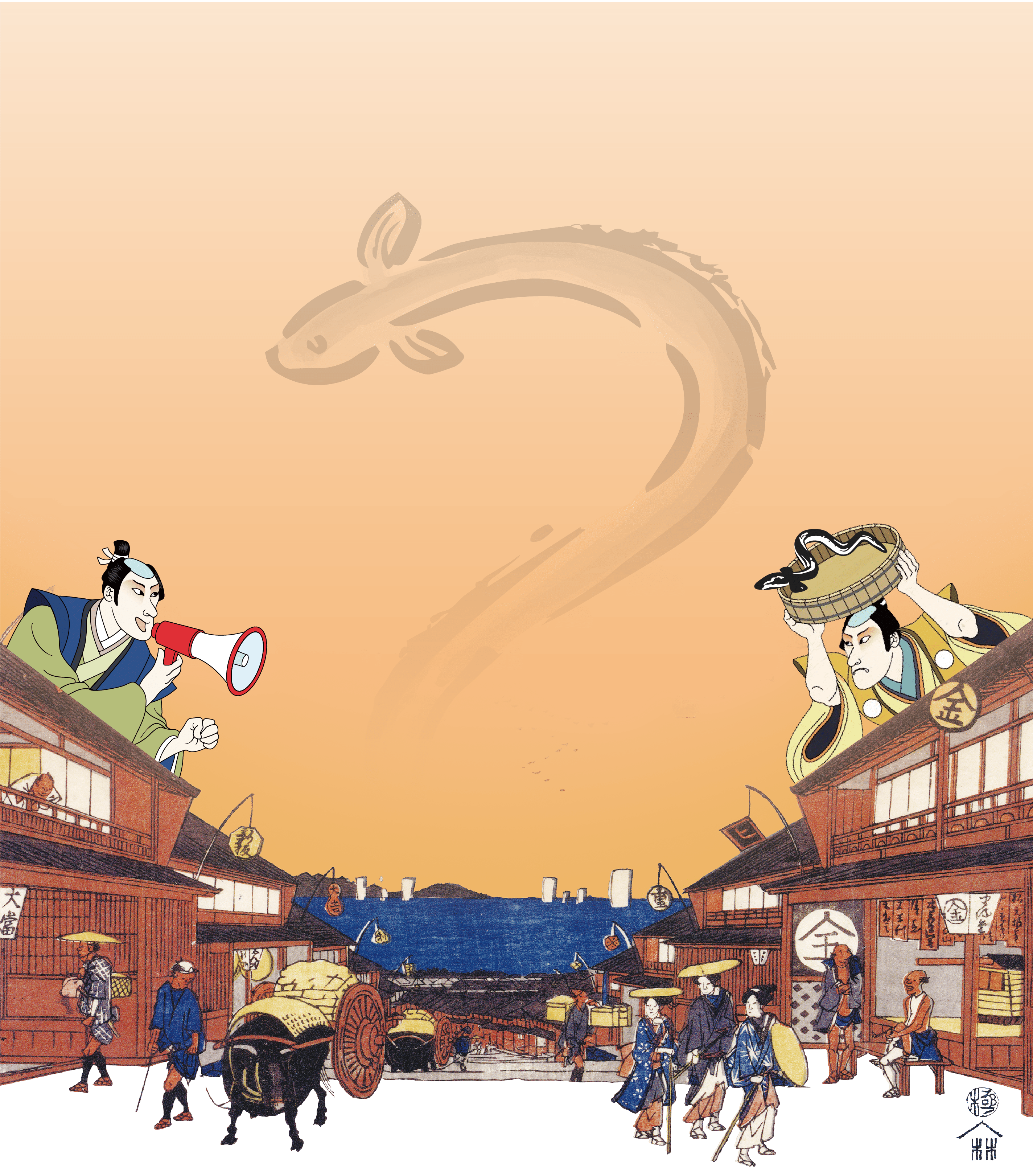
大津には昔から「湖魚・川魚」を扱う魚屋さんが多く存在し、人々は普段から湖魚や川魚を“琵琶湖の恵み”として食していました。
その恵みの 1 つに「うなぎ」があったのです。「近江興 地志略(おうみよちしりゃく)※1」には、黒津(瀬田川沿 い)の簗(やな)のうなぎ、堅田のうなぎが名産という記述 が、「淡海録(たんかいろく)※2」の特産品のページには瀬田の特産物としてしじみ、鯉、うなぎ....という文言が残されています。
※1・2 いずれも江戸時代に編纂された地誌。往時は東海道沿いから大津宿にかけて、琵琶湖や瀬田川で獲れたうなぎを扱うお店がありました。
琵琶湖に流れる川の水や清らかな湧き水を使った泥抜きの技術も、美味しいうなぎを提供できる秘訣だったのでしょう。
今もその名残から、東海道沿いには数々のうなぎ屋が店を構えています。
総務省の家計調査※3 では、大津市の「鰻の蒲焼き」の年間消費金額は全国でもトップクラスです。令和元年と令和2年には全国1位となりました。
最近では新たなうなぎ店も市内各所に見られるようになるなど、各店がこだわりの厳選うなぎを使い、食べた人の笑顔を誘っています。
※3 総務省家計調査 都道府県庁所在市別「うなぎの蒲焼き」/
文化庁が認定する、地域で世代を超えて受け継がれてきた食文化。
日本各地の多様な食文化を継承・振興することを目的としており、100年続く「100年フード」と名付けられています。
現在は琵琶湖や瀬田川でうなぎが獲れることはほとんどありませんが、うなぎを食べる食文化はこの地に息づいており、令和5年度に「大津のうなぎの食文化」として100年フードの認定を受けました。
もどき料理の一つで山芋などを使った蒲焼き「鰻もどき」は別名「せたやき芋」と言われ、有名な産地であった瀬田川で獲れた鰻の蒲焼きを「せたやき」と呼んでいたことからこの名が付けられたそうです。
瀬田の唐橋近くには、近江牛を使った「ひつまぶし重」をもどき料理?として提供しているお店もあります。